テーマ:「文脈のあるデザイン」
中野デザイン事務所代表/アートディレクター
中野 豪雄 氏Takeo Nakano
- PROFILE
- 大学在学中、身体性に深く関わる書物の構造に惹かれ、製本、印刷、タイポグラフィなど、書物形成における理論と実践を学び、卒業制作にて書物の歴史的変遷と分布の視覚化を研究する。現在、株式会社中野デザイン事務所代表。主な仕事に「世界を変えるデザイン展」「DOMA秋岡芳夫展」「more trees展」「コニカミノルタプラネタリウム天空のデザイン」等がある。日本タイポグラフィ年鑑グランプリ受賞。世界ポスタートリエンナーレトヤマ、ラハティ国際ポスタービエンナーレ、中国国際ポスタービエンナーレ、JAGDA年鑑、日本タイポグラフィ年鑑、TDC年鑑入選。東京デザインプレックス研究所プレックスプログラム登壇。

第1部:講義「文脈のあるデザイン」
講義1
2012年11月4日のプレックスプログラムの講師は中野デザイン事務所の中野豪雄さん。美大生時代にブックデザインに触れ、活字体・紙・印刷などの構造を学ぶにつれて本の奥深さにのめりこむようになったそうです。やがて“本”のカタチそのものを知りたくなったと、まずは自己紹介として実際に手掛けられたいくつかの作品を手に、デザインのポイントを解説していただきました。 大学時代の作品クオリティーに会場からはどよめきが起こる幕開けです。
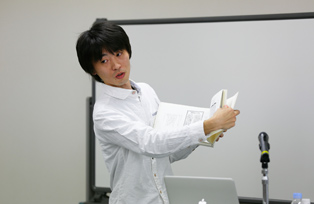
講義2
現在は、書籍のデザインや、展覧会や博物館の〈空間グラフィック〉などを手掛けている中野講師。 「展覧会における空間デザインの面白さは、一つひとつの作品はもちろん、作品同士の関連性、展覧会全体を通してのコンセプトを可視化し、来場者に伝えることができるところ」。デザイン論のみならず、展覧会の面白みも伝わってくるプレゼンテーションが展開中です。
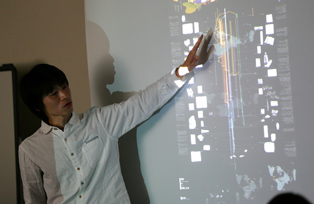
講義3
来場者が、展示会に足を運んだことで何かを気づき、発見し、自ら理解しようとする。さらにメッセージを伝えた先にはどのようなことがあるのか?といったところまで導いていけるデザインを心掛けているといいます。 中野講師の考えるグラフィックデザインの役割とは、「知ったつもりで終わらせないように、様々な角度からものごとを捉え、本質は何なのか、本当の理解へと自分で築いていける導線作りである」と語られました。

講義4
このようなことの重要性を確信したのが2010年6月、株式会社グランマからの依頼によって行った『世界を変えるデザイン展』の仕事だったそうです。難しく複雑な問題でも、情報を整理してグラフィックにおとすことで、来場者に理解を促すことができたと実感したと話す講師の言葉に、受講生たちは頷いたり、熱心にメモを取ったりしながら耳を傾けていました。

第2部:ワークショップ「日常の空間記述」
ワークショップ1
講義で述べた、さまざまな視点で捉えることを実践的に学んでいきます。事前課題として与えられていたキーワード「線・人・光・密集・動・内側」に、各人が30枚ほど撮った写真をプリントアウトして持参してきました。まずは写真を組み合わせてひとつの絵を作成する作業からスタート。 どう組み合わせるかでコンセプトを変えていきます。次に、同じキーワードのグループになり、それぞれどのような視点で課題に挑戦したか、ディスカッションを行いました。

ワークショップ2
1枚1枚の写真が独立したものでありながら、組み合わせることで新たな1つの作品になることを、実感していきます。わずかな時間の経過や変化が独特な表現になっていくことに、自分の作品はもとより、他の受講生の作品を見ることで気付かされます。受講生の作品も多種多様。例えば「密集」の課題では、徹夜で同じ場所(渋谷)に20分毎に30回撮影を行い、時間ごとの異なった空間を創りだす作品などがありました。

ワークショップ3
他に「線」の課題では、公衆電話を異なる角度から30枚撮影を行い組み合わせることで全く異なるモノを創り上げるなど気合いの入った作品も多く見受けられました。 また、チームごとのディスカッションにより、他者との捉え方の違い(新たな視点)があることに気づかされ、さまざまな角度からモノゴトを観る効果的な演習となりました。

総評
受講生の声をいくつか紹介。 「中野さんのお話を聞いて、私はミクロ的に物事を見ていたことに気がつきました」「ポスター・DM・本や空間まで幅広くデザインに関わるにはもっとマクロ的に全体像をとらえることが必要であると思いました」「事前の課題が大変だった分、やりきった感が今回はかなり感じられました。他の受講生たちが全く異なる視点で創ってきた作品が、とても勉強になりました」。

